
IUU漁業の「いま」と、飲食業にできること〜映画「ゴースト・フリート」パティマ・タンプチャヤクル氏 インタビュー

パティマ・タンプチャヤクル氏。LPN(Labor Protection Network:労働者保護ネットワーク)共同創始者。映画「ゴースト・フリート」におけるキーパーソン。(画像は、映画配給元のユナイテッドピープル様サイトより)
はじめに
一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会(以下、SRAジャパン)は、2023年に、IUU(違法・無報告・無規制)漁業の実態を描いたドキュメンタリー映画『ゴースト・フリート』の上映会を兵庫県芦屋市で開催しました。
本作でキーパーソンとして登場するのが、タイを拠点に漁業分野の人権問題に長年取り組んできたパティマ・タンプチャヤクル氏です。
上映会から3年が経過した現在、IUU漁業を取り巻く状況はどう変化しているのか。
そして、日々、魚介類を扱う飲食業には何ができるのか。
2026年1月19日、来日中のパティマ氏にお話を伺いました。
IUU漁業とは
“魚や貝、エビなど、世界のさまざまな水産資源は、近年減少の一途をたどっています。
その主な原因は、「乱獲」や「獲りすぎ」、すなわち水産資源の過剰な利用です。
この問題を解決するには、科学的根拠に従った実効性ある資源管理が必要です。
しかし、各国がそうした漁業管理を行なうための制度や法律を作っても、それが守られなければ意味がありません。Illegal, Unreported and Unregulated漁業、つまり、「違法・無報告・無規制」で行なわれるIUU漁業は、こうした資源管理の実効性を脅かしている、大きな国際問題のひとつなのです。
- 違法漁業(Illegal):国や漁業管理機関の許可なくまたは国内法や国際法に違反して行なう漁業
- 無報告漁業(Unreported):法律や規則に違反し、報告が行われていない、または虚偽の報告を行なう漁業
- 無規制漁業(Unregulated):無国籍または当事国以外の船舶が、規則および海洋資源の保全管理措置に従わずに行なう漁業
さらに、これらのIUU漁業においては、乗組員や漁業監視員(混獲や漁獲実態を調査報告するための調査員)の健康や生命を脅かすような人権問題も報告されるようになり、早急な対策強化が望まれています。”
出典:WWFジャパン 「IUU漁業について」 https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/282.html

聞き手:一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会 代表理事 下田屋 毅
「問題は今も続いている」――IUU漁業の現在地
――『ゴースト・フリート』公開から約9年、そして日本でのSRAジャパン主催の上映会から3年が経ちました。状況は改善しているのでしょうか。
この映画は公開以来、現在も世界中で上映され、LPNの活動を大きく後押ししています。
状況が劇的に変わったわけではありませんが、以前より人々が漁師の生活や問題を理解するようになりました。
映画は9年前の作品ですが、今もなお現在進行形の問題を描いていると感じています。
私は、この映画の上映のために、これまで20カ国以上を訪問してきました。映画と対話を通じて、多くの人がこの問題を理解し、「自分たちに何ができるか」と声をかけてくれます。
それでも残念ながら、問題はまだ終わる気配がありません。
現場では今もなお、賃金未払い、人身取引、暴力、薬物問題などが続いています。
またそれに伴い、父親に問題が起きると子どもたちがLPNに助けを求めてくるようになっています。
――現在、企業や行政との協働は進んでいますか。
企業の状況は、以前より多くの企業が人権デュー・ディリジェンスの実施の中で、人権のリスクを意識するようになり、監査や書類チェックは進んできています。
しかし、書類上は問題がなくても、実際には人権侵害が続いているケースが非常に多いです。
現地調査に入ると監視され、現場の担当者に自由に話を聞けないこともあります。
漁業の現場では、暴力や薬物問題が続いており、彼らは船の上では情報にアクセスできず、私たちは労働の実態を把握することができません。書類上は問題がなくても、実際には強制労働や暴力などの現代奴隷制が存在します。
LPNと企業との協働については、現在しっかりと実施・継続ができているのは、CPF(チャロン・ポカパン・フーズ グループ:総合的な農産物・食品事業を展開するタイ最大のアグリビジネス企業)だけです。LPNは、CPFと研修や予防活動を行っています。
企業は、水産物を購入する際、人権リスク(強制労働や人身取引)がないかを確認する必要があります。サプライチェーン上のリスクをチェックするという考え方です。それができている企業は現在(2026年1月)でもまだまだ少ないです。
政府機関とは、労働者保護の部署と連携し、通報があれば一緒に現場に入ります。ただし汚職の問題があり、問題を解決するには非常に難しい面もあります。そのため、メディアや中央政府との連携が不可欠となります。
――日本やヨーロッパ、アメリカの企業はLPNの活動に関心を持っていますか。
ヨーロッパ、アメリカ、日本の企業と協働できているかというと、関心は示していますが、対話の機会を持った上で「LPNと対話・連携している」とLPNの名前を使うだけにとどまり、実際の現場改善に結びついていないケースも多いです。またアイデアだけを持ち帰り、行動しない企業もあります。
書類チェックや監査だけで、漁業労働者の声が反映されていない場合もあります。
企業のCSR活動ではなく、実質的な変化を起こすことを考えなければなりません。

漁業労働者に話を聞く。「ゴースト・フリート」 インスタグラム@ghostfjp より
暴力や搾取のリスクにさらされる子どもたち
――LPNは個別ケースに対してどのような支援を行っていますか。
例えば、事故で片腕を失った漁師がいます。
母国に帰ることもできず、新たなスキルを身につけるための職業訓練が必要でした。
家族は借金を抱え、生活は非常に困難です。先月の現地調査でも、状況は依然として深刻で、薬物問題も拡大しています。
LPNは、法的助言、権利回復支援、シェルター提供(住居の確保)などを行っています。1つのケースに3年以上かかることも珍しくありません。
LPNは限られた資金の中で、こうした方に対しても長期支援を続けています。
法律は改善されたと言われますが、実際の現場では全く違うのです。
――私たちがすぐにできる支援があれば教えてください。
LPNが必要としているのは、必ずしも大きな資金には限りません。
例えば、「現地調査のための交通費」「子どもたちに配る文房具」「コミュニティの状況を把握するためのデータ収集の仕組みの支援」などです。
バンコクのインターナショナルスクールなどから寄付された文房具を配ると、子どもたちは本当に喜びます。
今後は、アプリなどを活用して、google mapのように、地域ごとの子どもの就学状況やリスクを可視化し、人身取引や強制労働の兆候を把握できる仕組みを作りたいと考えています。
漁業・水産業は非常に閉鎖的で、子どもたちは暴力や搾取のリスクにさらされています。しかし、その実態はコミュニティの外から把握することができず、記録もされていないので、支援が届かないケースが多くあります。
だからこそ、現場に入り、データを集め、社会に伝えることが不可欠なのです。

2023年2月19日(日)、日本サステイナブル・レストラン協会主催、WWFジャパンの後援により、「映画『ゴースト・フリート』上映とサステナブルなシーフードについて考えるトークショー」を開催。
飲食業が、できることとは
――この問題の解決のために、飲食業はどのように関わればよいか、お考えをお聞かせください。
レストランやホテル業界はサプライチェーンの最終地点(消費側)なので、原材料の背景を知ることがとても難しいです。
だからこそ、シェフや業界関係者の意識を高めることは重要です。
そのために、この問題があることを知り、映画上映会に参加すること、シェフ向けの対話やトレーニングはとても有効だと思います。
また、食事イベントやチャリティディナーを通じて、寄付金を送ることも有効です。その資金で、漁業コミュニティを支援することができます。

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会 下田屋と、パティマ氏。2人が手にしているのは、困難な状況にある子どもたちが描いた絵がデザインされたTシャツ。暴力や搾取のリスクにさらされる農業・漁業労働者の家庭、戦争から逃れてきた子どもたちのことを知ってほしい。
インタビューを終えて
SRAジャパンとしては、2年ぶりのパティマ氏との再会となりました。変わらずエネルギッシュに問題に取り組んでいるお姿に心が動かされます。
IUU漁業の規模は、日本に輸入される水産物のうち24~36%(*)を占めているといいます。私たちも知らず知らずのうちに、こうしたIUU漁業由来のシーフードを口にしている可能性があるのです。(*https://www.wwf.or.jp/activities/data/20240209_sustainable01.pdf)
まずは、1人でも多くの方にこの現実を知っていただくことを続けていくことが必要だと、あらためて感じました。
映画と対話を通して、食のサステナビリティを考える
SRAジャパンでは、映画と対話を通して食のサステナビリティを考えるイベント「FOOD MADE GOOD映画祭」を東京で定期開催しています。
このIUU漁業の実態をより多くの方に知っていただくため、次回の上映作品は、映画『ゴースト・フリート』を予定しています。
当日は、パティマ・タンプチャヤクル氏にも登壇いただき、特に飲食業に関わる皆さまとともに、
「私たちの食の選択」について考える場としたいと考えています。
またレストラン「レフェルヴェソンス」エグゼクティブシェフ、SRAジャパンの理事でもある、生江史伸氏をお招きします。生江氏は、IUU漁業に関心を持ち、タイの現場も訪れるなど、行動を起こしているシェフです。
そして、IUU漁業の撲滅に向けてグローバルに活動する、WWFジャパン様からは、滝本麻耶氏にご登壇いただき、IUU漁業の実態をデータとともに解説していただきます。
次回のFOOD MADE GOOD映画祭は、映画『ゴースト・フリート』上映とトークセッションは、2026年2月24日(火)開催です。
パティマ氏と直接対話ができる、大変貴重な機会になります。トークのあとは、サステナビリティに配慮され、トレーサビリティが確保された魚介類を使った軽食をお楽しみいただきながら、登壇者および参加のみなさま同士の交流のお時間を設けています。
詳しくはこちらをご覧ください。


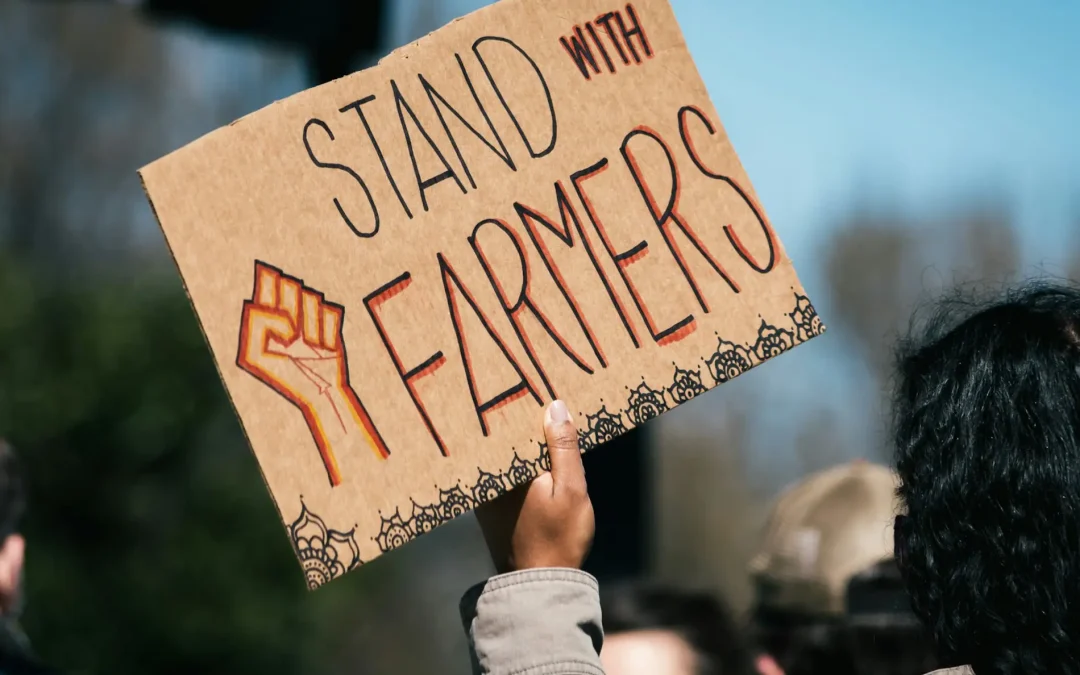


最近のコメント