サステイナブル・レストラン協会では、FOOD AMDE GOODスタンダードを実践する加盟店のインタビュー記事を定期的にお届けしており、今回、ジターリア・ダ・フィリッポ(東京都)が紹介されました。「従業員の公平な評価・処遇」について、どのように考え、実践しているのか、ジターリア・ダ・フィリッポの岩澤オーナーシェフのインタビューをご覧ください。
ピッツェリア・ジターリア・ダ・フィリッポは、東京都練馬区にあるレストランで、「伝統的特産品保証(STG)」の基準に則ったピザを提供しており、使用する小麦は100%国産です。
2023年に初めて「フード・メイド・グッド・スタンダード(Food Made Good スタンダード)」の審査を完了し、特に「スタッフを公正に扱う」分野で高い評価を獲得しました。
私たちは「ピッツェリア・ジターリア・ダ・フィリッポ」のオーナーである岩澤正和さんに、慎重な配慮、オープンな対話、従業員の主体性を通じて、いかに活気ある職場を築いているかについてお話を伺いました。
「Gtaliaでは、サステナビリティは“人を大切にすること”から始まると考えています」と語るのは、ピッツェリア・ジターリア・ダ・フィリッポのオーナーシェフ、岩澤正和さん。
「特に飲食業界では、料理の裏側には必ず“人”がいます。畑で野菜を育てる人、厨房で料理を仕込む人、ホールでお客様を迎える人。その人たちが尊重され、大切にされていなければ、心のこもったサービスを提供することなどできません。」
岩澤さんは長年、ホスピタリティ業界の最前線で働いてきた経験を持ち、努力が正当に報われない現実を目の当たりにしてきました。
「飲食業界は、長時間労働、不明瞭な評価制度、そして声が届かないという構造的な問題を抱えてきました。Gtaliaではそうした“当たり前”を問い直し、すべての人が健康的に、平等に尊重されながら働ける職場を目指しています。」
「料理の裏には“人”がいる。畑で野菜を育てる人、厨房で仕込みをする人、ホールでお客様を迎える人。
その一人ひとりが尊重され、大切にされなければ、心を込めたサービスは成り立たない。」
Gtaliaにおける「スタッフの公正な評価・処遇」取り組み
この哲学は、日々の業務やスタッフとのコミュニケーションの中に反映されています。
「言葉の選び方から働き方の設計に至るまで、すべての判断の軸に“人”を置いています。」
■ 従業員評価
Gtaliaでは、職位や数字に縛られない評価制度を導入し、仕事への満足感と個人の成長を促進しています。
「私たちは、マネジメントの期待に応える人だけでなく、他者を支える人もきちんと評価する文化をつくりたいと思っています」と岩澤さん。
評価は、行動・学び・挑戦・貢献という4つの柱を軸に、マネージャーとの1対1の対話を通じて自己評価とすり合わせながら進めます。
「これらは単なる二択式の判断ではなく、“意図”と“成長”を重視した振り返りの時間です。」
■ 学びと成長の機会
新人から中堅、リーダー層に至るまで、Gtaliaではスキル研修だけでなく、農業体験、地域訪問、店舗間交流などを通じて、感情的・人間的な成長も支援しています。
「これらは単なる技術研修ではなく、“食と社会”の関係を学ぶ機会でもあります」と岩澤さん。
こうした継続的な学びに加えて、現場からの提案を経営に届ける仕組みも整備されており、スタッフが主体的に店舗運営に関われるようになっています。
■ 承認と報酬
口頭および書面での「感謝」と「承認」が推奨されており、たとえば「Thanksカード」制度を導入し、マネージャー以外のスタッフの活躍も可視化・評価しています。
このカードは、年齢や役職に関係なく、スタッフ同士が互いの良い行いに感謝の気持ちを伝えるもので、評価や賞与の判断にも活用されています。
「今年は、受賞者に地元の商店街からの特別賞や蒸留所で入手した希少なウイスキー、商品券などを贈りました。」
■ みんなで「食べる」時間
Gtaliaでは「まかない」を、単なる福利厚生ではなく、スタッフの健康と学びを支える“制度”と位置づけています。
管理栄養士の指導のもと、週ごとにテーマとなる野菜を設定し、それに基づいた3品構成の野菜中心の食事を提供。旬の食材や栄養について学ぶ機会となっています。
「調理はキッチンとホールのスタッフが交代で担当し、それぞれの個性が料理に反映されるようにしています」と岩澤さんは語ります。
ワーク–ライフ・バランス
岩澤正和さんは、「従来の飲食業とは大きく異なるスタイルで、多様なライフステージに寄り添う雇用環境を設計している」と説明しています。
「私たちは『全員に同じ一律の働き方』を推進しているのではなく、『人生を尊重する働き方』を志向しています。たとえば、共働きの親向けに朝シフトを提供したり、外国人研修生への言語・生活面のサポートを行ったり、夢を追う若手シェフには柔軟な勤務スケジュールを設けたりしています。」
将来的には、健康や家族、個人の夢をより支えるために「週4日勤務」への移行も検討しているとのことです。
「私たちは一律の職場環境を信じるのではなく、人生を尊重する雇用を目指しています。」
この方針は、単なる社内文化にとどまらず、「働く人が未来を創る」という信念に基づいた書面化されたポリシーとして明確にされています。
「これは単なる評価制度ではなく、日常業務に根付かせる文化的変革です。これらの取り組みは政策ではなく、人間性を尊重する私たちの根本的な信念の表れです。共通しているのは、『評価の前に理解ありき』という考え方です。公平さは画一的なルールから生まれるのではなく、それぞれの人生を尊重することから生まれます。」
スタッフを公正に扱うことで得られる業務上の恩恵
「スタッフの扱い方を変えることで、飲食業界を変革できると私たちは信じています。」と岩澤さん。
実際に、定量・定性の両面で変化が見られ、とりわけ離職率の劇的な低下がその象徴です。
「以前は年間で10名以上辞めていましたが、2020年以降では年間2~3名程度に減少しました。特に若手スタッフに長く働きたいという意欲が強まり、中堅育成が安定してきました。」
外部からの評価も高まっています。GoogleレビューやアンケートではGtaliaスタッフの明るさや真摯さが数多く言及されています。
「これは、スタッフが“人としてのあり方”で本音で向き合える環境にいることの表れです。」
同店は『Food Made Good Japan Awards』でも2023年と2024年に“BEST 社会賞を受賞し、業界関係者が見学に訪れたり、価値観に共感して求人応募にいたる例も増えています。
「これらの成果は、“人を中心に据えた経営”がスタッフにもお客様にも社会にも利益をもたらす、という私たちの信念を裏付けています。」
“人を中心に”経営する難しさ
岩澤さんによれば、最も大きな課題は「業界慣習」と「理想」の間のギャップを埋めることでした。
「飲食業界には依然として“長時間労働・低賃金・縦社会”の常識があります。若手や未経験者にとっては、『飲食業で幸せに成長する』というイメージが湧きにくいのです。」
そこで「食に誇りを持つ職場」ハンドブックをスタッフとともに制作し、飲食の仕事の価値を見える化・共有可能にしました。これは新人研修や採用時、社内コミュニケーションなどで活用されています。
スタッフと経営者が対話できる場も設けられており、毎月の対話ミーティングと1対1面談が継続的に実施されています。そこでは、気づきにくい不満や懸念も顕在化しています。
岩澤さんは、古い慣習の中で働いてきた経営者やマネージャーへの共感と理解も重要だと強調します。彼らが新しい働き方に適応しやすいよう、SNSやブログを通じて、“罪悪感を煽らない”形で、飲食業の喜びや誇りを共有しています。
「これらの課題を“対話の機会”として捉えることで、社内外の理解を広めてきました。」
業界慣習を変える
「私たちの目標は、自分たちの職場を改善することだけではなく、“私たちが誇れる業界”をつくることです。」
岩澤さんは続けます。
「サステナビリティや公正な職場に関して、業界全体が共通の認識をもつことが、次のステージへの前進につながると強く信じています。」
そのためには、対話の場や知識共有が不可欠です。Gtaliaでは、他のレストランとともに“働き方”について共に学ぶ会や対話会を開催し、“人を主体とした文化”構築の実践を共有しています。
「これらの場は、『これは理想論ではなく、実現可能なことだ』と他者に安心を与え、行動の勇気につながっています。」
また、農家や地域と連携して“働く=生活”を感じられる場づくりも進められています。
「都市の飲食店と地域の生産者をつなぐことで、スタッフやお客様にも新しい価値観や視点への接点が生まれ、飲食業界全体の可能性を拡大しています。」
協働がすべて
岩澤さんはこう締めくくります。
「これからは、正しいことをする人が孤立しない仕組みが必要です。SRAのようなプラットフォームは、意味ある変化に取り組む人々をつなぎ、評価する重要な役割を果たしています。私たちはそのネットワークの一員であることを誇りに思い、今後も貢献を続けていきます。」
「SRAのようなプラットフォームは、意味ある変化に取り組む人々をつなぎ評価する上で極めて重要です。私たちはその一員であることを誇りに思い、貢献し続けたいです。」
ピッツェリア・ジターリア・ダ・フィリッポのFood Made Good
同店は2023年に『Food Made Good Standard』の初評価を受け、最初の試験で三つ星を獲得しました。
「直感的に良いことをするだけでなく、グローバルなベンチマークを通じて可視化したかった」と岩澤さん。
日本の飲食業では、“職人の美徳”が経験や口伝で継承されることが多いですが、これは持続可能性の視点から見ると再現性や説明責任の面で限界があります。
「このスタンダードは、ただのチェックリストではなく、レストランの全体運営を見直す“レンズ”として機能します。」
認証後、同店では内部・外部の利点を実感しています。岩澤さんは意識変化を特に大きな成果としています。
「スタンダードの全体像を共有したことで、スタッフは『意味ない』という気持ちから『これは大切で長期的な価値がある』という意識に変化しました。」
2022–2024年の間に、内部研修の参加率は平均80%から120%超にまで上昇し、アルバイトスタッフも意欲的に参加するようになりました。スタッフは自らの仕事の社会的価値を言語化できるようになっています。
具体的に見えてきた恩恵
- 採用のしやすさ
「Food Made Goodに取り組む職場で働きたい」と志望する応募が増え、特に学生や若手からの応募が増加しています。Instagramのフォロワー数はスタンダード取得後、30%増加しました。
- 連携と知見共有の拡大
SRA Japanや他の持続可能レストランとの協働が活発化し、共同プロジェクト・情報交換の場が増えました。
海外のサステナビリティに関心あるシェフやジャーナリストとの接点も生まれています。
Gtaliaの未来展望
Gtaliaでの取り組みはまだ途上です。
異なるライフステージや価値観を持つ人々が活躍できるよう、さらに雇用モデルを磨いていきます。
共働きの親向けシフトや、高齢者・障がい者への個別的な就業設計なども強化中です。
「これは単なる人手不足対策ではなく、チームのレジリエンスと強さを深めることでもあります。」
将来に向けては「次世代のための共育の場」を構築したいと考えています。
地元の中高生向けのインターン制度や、経済的に恵まれない家庭の子ども向け無償ピザ教室、『自分の未来をデザインする』プログラムなどが計画に含まれています。
「私たちの信念は、飲食業こそが人々の人生を本当に豊かにできる場であるべきだということです。」
「サステナビリティとは大きなジェスチャーではなく、日々の小さな選択の積み重ねです。私たちはチームとともにその小さな選択を積んでいきます。」
対話を終えて岩澤さんはこう語りました:
「Gtaliaの実践が“特別なもの”としてではなく、当たり前のものとして受け入れられるようになってほしい。私たちは、小さな取り組みを確実に重ね、それらを共有し、仲間と協働することで未来をつくっていきます。サステナビリティは大きなジェスチャーではなく、日々の小さな選択の積み重ね。その選択をチームと一緒に続けていきます。」
。






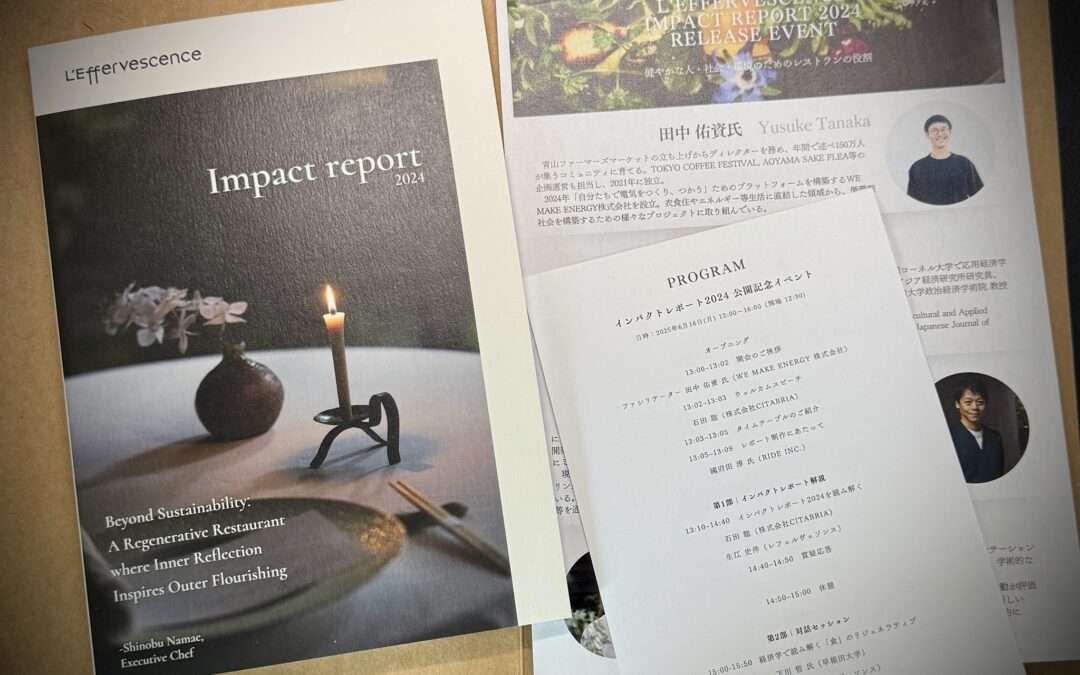
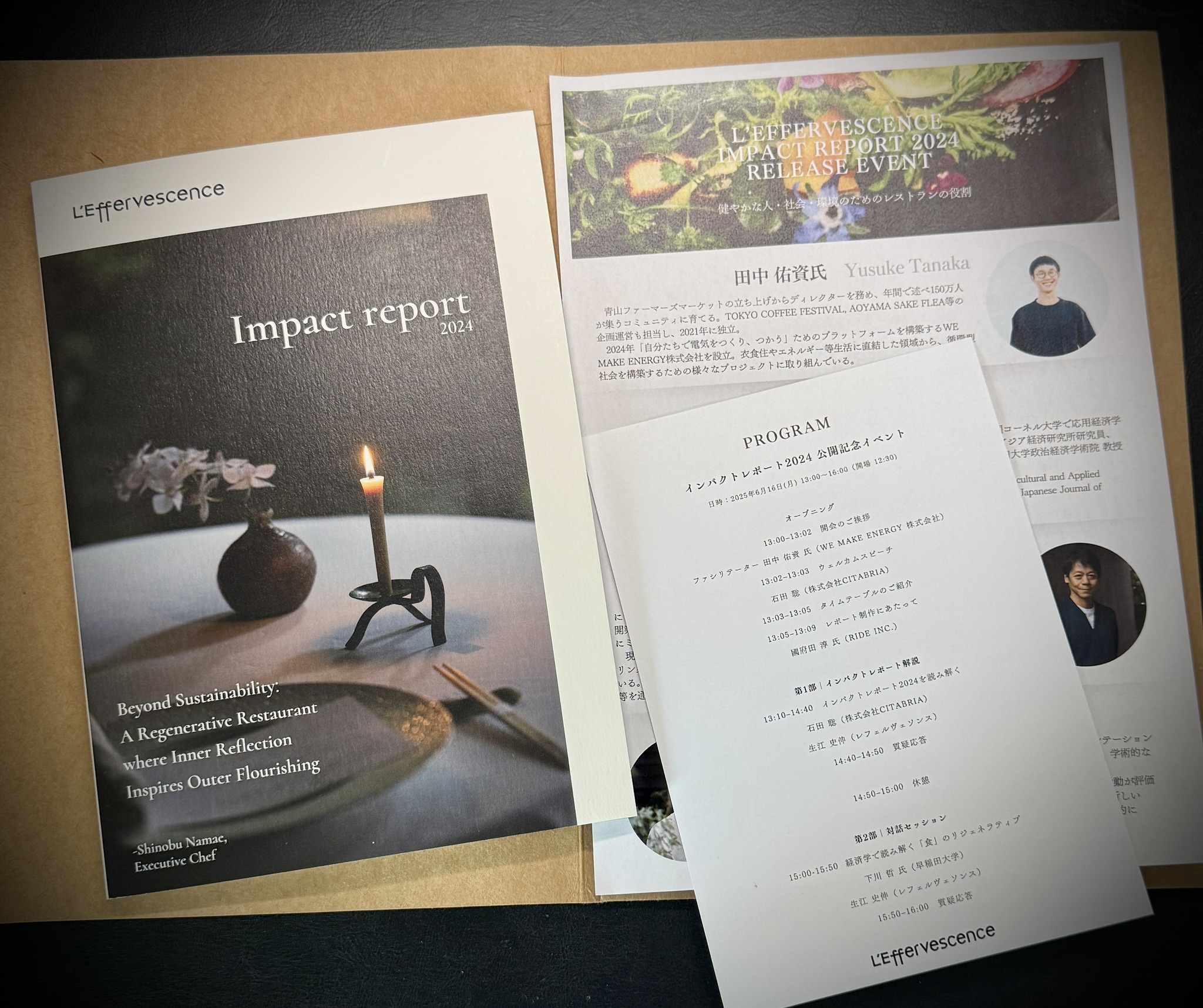




最近のコメント